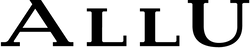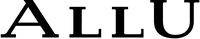隈研吾
ALLU Story
隈研吾
1954年生まれ。1990年、隈研吾建築都市設計事務所設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現在、東京大学特別教授・名誉教授。30を超える国々でプロジェクトが進行中。
自然と技術と人間の新しい関係を切り開く建築を提案。主な著書に『全仕事』(大和書房)、『点・線・面』、『負ける建築』(共に岩波書店)、『自然な建築』、『小さな建築』(共に岩波新書)、他多数。
変わりゆく建築の在り方
変わりゆく建築の在り方
サステナビリティを語る時に前景化しやすいイシューは、地球環境や気候変動であろう。建築の分野においては、建築物にかかるカーボンフットプリントや建材がいかに地球環境へ配慮しているかなどの視点で語られることは多い。しかしサステナビリティには、人種やジェンダーにまつわるイクオリティ、産業構造や労働環境の持続可能性、ウェルビーイングなど、多岐にわたる論点が含まれる。世界的な建築家である隈研吾が、そうした課題が社会の中で表出するはるか以前から、建築がいかに人にとって持続可能なものであるべきかを自問してきたのは、自身が経験したバブル崩壊が大きな教訓となっているからだ。
「僕が事務所を始めたバブル期にはギラギラとした建物が次々と生まれていたんだけれど、バブル崩壊後にそれらを手掛けた建築家達が次々と背を向けていくのを見て、なんともいえないむなしさを感じたんです」。
バブル崩壊とともに、日本経済の隆盛を如実に象徴していたそれまでの建築の在り方が、まさに幻であったかのように崩れていく。その様を間近で目撃していた、独立して間もない隈は「それから10年間は東京での仕事がほとんどなかった」と当時を振り返るが、その時に得た地方の仕事が、彼の考えに大きな影響を与えた。
「1990年代の僕のメルクマール的な仕事に、『石の美術館』があります。栃木の小さな石材屋さんから、自分の家の庭にある、放置された石蔵を使って美術館をつくりたいと依頼があったんです。驚くことに、それにかかる工事費の予算は『0円』だった。自分の庭にある石を使って、石工の依頼主と職人のおじいさんがやるから0円ということだったんだけど、それを聞いた僕はなかなかショックでね。でも、だからこそ、職人でもある彼等と一緒に、彼等にとって本当に意味のある新しいものを妥協なくつくることができて、それが世界的にも評価をしてもらえた。それが、『人間の身体を中心に考える』という僕の根底を築く1つのきっかけになりました」。
「サン・モーリス大聖堂」
フランス西部のアンジェにあるサン・モーリス大聖堂の歴史ある扉を保護することを目的に、隈研吾建築都市設計事務所がギャラリーを設計した。サン・モーリス大聖堂で近年発見された中世の建築遺産である、多色刷りの彫刻を保護しながら、ロマネスク、ゴシック、現代という複数の時間の層を重ね合わせ、調和を生み出す試みがなされている。設計にあたっては、中世の建築家達と同じくコンパスを用いるというプロセスが採用された。
© 藤塚光政
人間の身体から、
直感的な美しさを問う
人間の身体から、直感的な美しさを問う
「シラコノイエ」
千葉県の外房にある登録有形文化財「旧大多和邸」の改修を通して、日本の美しい暮らしのケーススタディ・ハウスを目指したプロジェクト。循環をテーマに、訪れた人の心身を癒すリトリート施設として、隈研吾建築都市設計事務所の設計の下、プロジェクトメンバーと職人、ワークショップ参加者など多数の人が交わりながら、千葉の風土と日本の伝統技術に向き合って改修が行われた。
「人間の身体以外の無駄なものは省いていく」「身体にしっくりくるものだけを身の回りに置いていく」。隈が築いてきた“美しさ”へのアプローチは、サステナビリティを考えるうえでも非常に重要だと隈は指摘する。
「科学的な根拠とアプローチで持続可能性を生み出していくことも重要だけれど、僕はもっと、美しいとは、かっこいいとは何か、どんなものが愛せるのか、人間にとって何が一番しっくりくるか、そんな直感に従ってアプローチしてきました。それが時代の流れのなかで数値的な裏付けが伴い、いわゆるサステナビリティとして語られることになった。ですから、僕はやはり自分の直感を信じたいし、その直感を養うには“手を動かすこと”が大切です」。
手を動かすからこそ、建築家は直感的に、サステナビリティへアプローチを問うていくことができる。隈は、この身体を起点にした直感の重要性を、現在の都市空間における建築業界の産業的な課題を引き合いに強調する。
「今の東京は、世界で一番つまらない都市空間になりつつあります。かつては、家を建てる人(大工)がクライアント(生活者)と共に一緒に考えて家をつくっていた。建築と生活の一体感があったんです。それがゼネコンや建設会社が登場してから、建築がマネジメントの世界になり、人間から遠いものになっていった。ゼネコンも発注担当者も失敗のリスクを背負いたくないので、『商品』である建築はより画一的になり、高価格になっていく。専門性をもった人しか空間をつくれなくもなる。これはすごく不幸なことですよ」。
「時間」が味方をしてくれる
「時間」が味方をしてくれる
自分の手で空間をつくれるようにならなければ、都市はつまらないものにしかならない。都市がつまらなければ、持続可能な社会など生まれようもない。だからこそ、隈は人間の手、身体から離れず、人にとって本当に持続可能な建築のアプローチを模索し続けている。現在隈が携わる、千葉県外房にある登録有形文化財「旧大多和邸」の再生プロジェクト「シラコノイエ」も、建築家自ら手を動かしながら得た美しさへの直感を設計に投影し、建築を一部の特権的なものから「ふつうの人」の手のもとに取り戻すための試みだ。
「建築家というものは、頭でっかちに社会や建築を考える人が多いから、僕達も、それをなんとかして超えたいと思っています。『シラコノイエ』は隈研吾建築都市設計事務所にとって、“頭”から“手”を使った設計への転換を試みる、初めての本格的なプロジェクトなんです。
リノベーションや古いものの活用というのは、設計以上にプロセスに手間がかかるものです。しかし、今日やれることから始めて、先人の知恵や技術を身体的に受け継いで新しさを見出していくこと。それによって、そこにすでにある美しさやそれを培った時間が味方をしてくれる。そう思っています」。